■「もしもノンフィクション作家がお化けに出会ったら」工藤美代子/角川文庫
工藤美代子さんは、吉田茂、笹川良一、昔のラフカディオ・ハーンなどを独特の視点で取り上げてきたノンフィクション作家。
この方の書く文章ってほんと、ほれぼれして憧れてしまう。
ストレートでリズミカル。
あがいた後をみじんも見せない意気のよさ。
読者に甘えるかのような行間のない整った調べは、数式のもつ美しさにも通じる。
安心して身を任せて意中の旅ができる、最高に整備された心地のよい乗り物のような。
それを言うならこの言い方しかないというか、書いている本人のストレスを感じないというか、制動が利いていながら、伸びやかというか。
これは、たぶん、事実を語るノンフィクションをずっと書いてこられたからなんだなとも思います。
この本の冒頭で、ノンフィクションを書くにあたっての心構えとしている「絶対にウソはだめ。一語たりとも」というのを、エピソードを交えて語っています。
それがいかに難しいかもよくご存知なのです。どうしても、ストーリーへの欲望を抑えきれないのが、書くということですから。
その工藤さんがみずからの不思議体験を、自分のノンフィクションとして表したのがこの本。
不思議体験というのは、オカルト。工藤さんは幼いころから、この世にいない人、ものを見るという人なんです。
ウソを書けないというノンフィクション作家の矜持を冒頭に堂々と宣言し、ノンフィクションとしてのオカルトを書き表していきます。今回はお遊びの仕事です、という趣が一切ない。
病院での数々の体験から、飼っていた犬が部屋に現れる話、夜中にボール遊びをする女の子、それから、三島由紀夫も登場します。
いわゆる怪談本なんですが、その語り口は非常に淡々としたもの。
しかし、こうしたオカルトの読み手が期待する人情噺にも触れながら、あちらの世界とこちらの世界、これを縦と横に織り上げていきます。
こうしたオカルト話に人が惹かれるのは、ファンタジーを求めてのこと。
この世のものでない方との接触を思うと、未経験の土地に旅をしたときのような、すごい解放感がある。
でも、旅っていうのは、帰る土地があるから旅。時々、違う世界を行きつ戻りつする、呼吸のようなもの。
非日常の旅先で感じるものも、日常世界に根を持つ何かの象徴でしかない。
この本で取り上げられたあちらの方々との出会いでさえ、この世に生きていた時の愛憎の感情抜きのものはない。
ただ、この工藤さんのように、日々実際に体験をしている人にとっては、オカルトはとんでもないことで、いい加減うっとおしくて仕方がない。いきなり日常生活を寸断されて迷惑。見なくて済むならそれに越したことはない、と思っている。
だって、「見える人」にとっては、解放をもたらす旅などではなく、リアルな日常の現実でしかないのですからね。
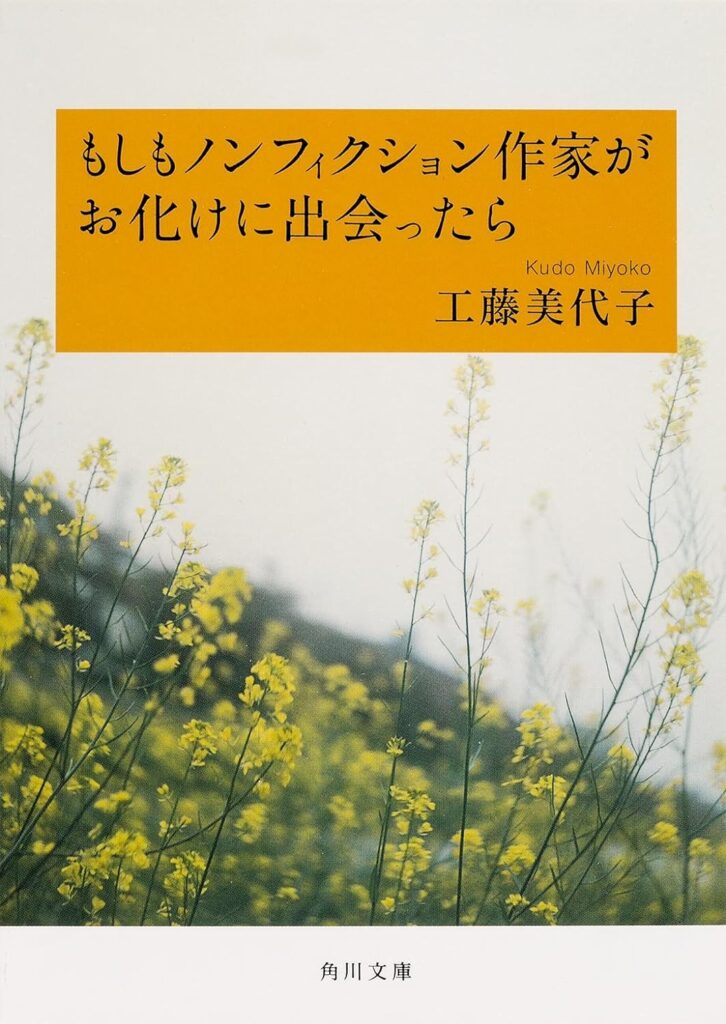
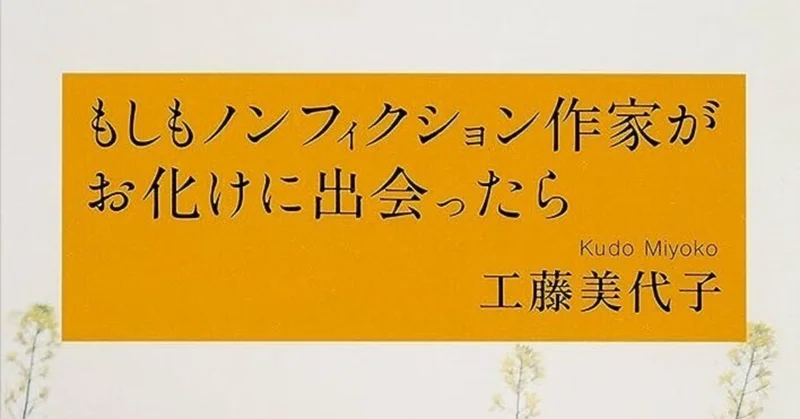

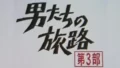
コメント